昔の着物の文化を解明!歴史や暮らしの不思議に迫る

「昔の着物って、今とどう違うの?」「着物が普段着だった頃の生活ってどんな感じだったんだろう?」そんな疑問を感じたことはありませんか。着物 昔の歴史を紐解くと、単に昔と今の違いが見えるだけでなく、妊娠中の工夫や、なぜパンツを履かないのが普通だったのか、さらには寝巻きとしての役割や洗濯方法まで、当時の人々のリアルな暮らしが浮かび上がってきます。この記事では、昔の着物の特徴を時代背景と共に詳しく解説し、あなたの知らない着物の世界の扉を開きます。
- 昔の着物の時代ごとの特徴がわかる
- 現代との着こなしや文化の違いを理解できる
- 妊娠中や下着事情など昔の暮らしぶりがわかる
- 古い着物の価値や扱い方のヒントが得られる
昔の着物の姿を知る:歴史と変遷
現代では結婚式や成人式など、特別な日の衣装というイメージが強い着物ですが、ほんの数十年前までは日本人の日常に深く根付いた衣服でした。その形は、時代の移り変わりや人々の価値観を映し出しながら、少しずつ変化を遂げてきたのです。ここでは、古代から近代に至るまで、着物がどのように形を変え、私たちの暮らしと共にあったのか、その壮大な歴史と変遷をたどります。
- 着物の歴史を時代ごとに解説
- 昔の着物の特徴とは?
- 昔と今の違いを比較してみよう
- 時代で変わる色や柄のトレンド
- 身分で異なった素材と仕立て
着物の歴史を時代ごとに解説
日本の着物の歴史は非常に長く、その起源は縄文時代にまで遡りますが、現代私たちが知る形の原型が生まれたのは平安時代です。気候風土や社会構造の変化に対応しながら、独自の進化を遂げてきました。ここでは、各時代の背景と共に着物がどのように変化してきたのかを、詳しく解説していきます。
古代~平安時代:着物の原型が誕生
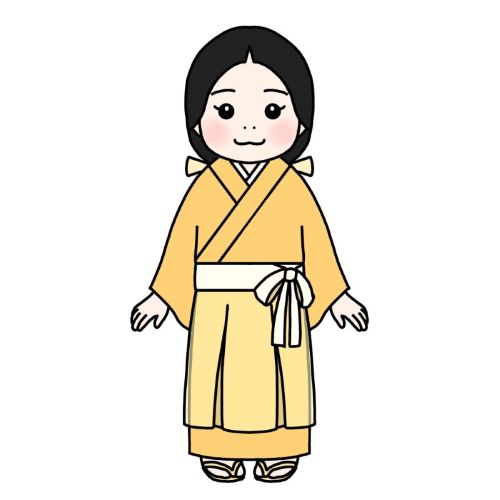
飛鳥・奈良時代には、遣唐使を通じて中国大陸の進んだ文化が取り入れられ、服装も唐の衣服(漢服)の影響を強く受けました。しかし、奈良時代の719年に発令された「衣服令(えぶくりょう)」により、襟の合わせ方を身分に関係なく「右前(右の身頃を先に合わせる)」に統一するよう定められます。これが現代まで続く着物の基本的なルールの始まりです。
その後、平安時代に遣唐使が廃止されると、日本の気候や文化に合わせた独自の「国風文化」が花開きます。この時代に生まれたのが、「直線裁ち」という画期的な技法でした。これは、一反の布を無駄なく直線的に裁断して縫い合わせる方法で、体型を問わず着用でき、解けばまた一枚の布に戻せるという、非常に合理的でサステナブルな特徴を持っています。貴族社会では、十二単(じゅうにひとえ)に代表される重ね着の文化が発展し、「襲の色目(かさねのいろめ)」と呼ばれる色彩の組み合わせで、季節の移ろいや個人の教養を繊細に表現していたのです。
鎌倉~江戸時代:武家と庶民の文化が花開く

鎌倉時代に入り、貴族に代わって武士が社会の中心になると、衣服は儀礼的なものから、より動きやすく実用的なものが求められるようになります。これが、現代の着物の直接の祖先である「小袖(こそで)」が、それまでの下着的な役割から表着として定着する大きなきっかけとなりました。
そして江戸時代、泰平の世が続くと、着物文化は庶民の間で大きく花開きます。経済力を持った町人たちは、友禅染や絞り染め、刺繍といった高度な技術を用いた着物で、身分制度の枠内で許される最大限のオシャレを楽しみました。幕府による贅沢を禁じる「奢侈禁止令」が度々出されると、一見すると地味な色や柄の中に、裏地や見えない部分で凝る「粋(いき)」という独特の美意識が生まれ、より洗練された文化へと昇華していきました。
「小さい袖」という意味ですが、袖の長さが短いわけではありません。袖口(そでぐち)が小さい(狭い)ことから、そう呼ばれました。これに対し、平安貴族が着ていた袖口が大きく開いた衣服は「大袖(おおそで)」と呼ばれます。
明治~現代:洋装化と伝統衣装への道

明治時代になると、開国と共に西洋文化が怒涛のように流入し、政府は近代化政策の一環として役人や軍人に洋装の着用を義務付けます。しかし、庶民の間では依然として着物が主流であり、海外から輸入された化学染料の導入によって、それまでにはなかった鮮やかな色の着物が作られるようになりました。
大正時代には「大正ロマン」と呼ばれる、和洋折衷のモダンで自由なスタイルが流行します。昭和に入り戦争を経て、戦後の高度経済成長期に国民の生活が一気に洋風化すると、着物は日常着としての役割を終え、成人式や結婚式など、人生の節目を彩る「ハレの日」の特別な衣装へとその立ち位置を変えていきました。
| 時代 | 主な特徴 | キーワード |
|---|---|---|
| 平安時代 | 直線裁ちの確立、重ね着文化(十二単)、国風文化の発展 | 国風文化 |
| 鎌倉・室町時代 | 実用性を重んじる武家社会の台頭、小袖が主流に | 武家社会 |
| 江戸時代 | 町人文化の発展、友禅染などの技術革新、「粋」の美意識が生まれる | 庶民文化 |
| 明治・大正時代 | 西洋文化の影響、化学染料の導入、和洋折衷のモダンなスタイルが流行 | 大正ロマン |
| 昭和~現代 | 日常着から礼装・ハレ着へ。生活様式の変化に伴う役割の変容。 | 生活の洋風化 |
昔の着物の特徴とは?
昔の着物には、現代の着物とは異なる多くの特徴があり、その根底には「モノを大切にする心」と「長く使い続ける知恵」がありました。最大の特徴は、「着る人に合わせて仕立て直す」ことが前提であった点です。布を大切にし、一つの着物を世代を超えて着続けるための工夫が随所に凝らされています。
素材は、絹、麻、木綿といった天然繊維が中心でした。特に庶民の間では、丈夫で扱いやすい木綿や、夏涼しい麻が広く使われていたのです。染色も、藍や紅花、蘇芳(すおう)といった植物由来の染料が主で、職人の手作業による温かみのある、一つとして同じではない風合いを持っていました。
前述の通り、「直線裁ち」で作られているため、縫い目を解けばほぼ長方形の布に戻ります。これにより、仕立て直しや他のものへの再利用(リメイク)が非常に容易でした。例えば、大人の着物を子どもの着物に仕立て直したり、着物としての役目を終えた後は、座布団や布団の側、最終的にはおむつや雑巾として、布が擦り切れるまで大切に使い切るなど、驚くほどサステナブルな衣服だったのです。
また、現代のようにTPOに合わせた多くの種類の着物を所有するのではなく、限られた着物を帯や半衿、帯締めなどの小物を変えることで巧みに着回していました。季節に合わせて裏地を付けた「袷(あわせ)」と裏地のない「単衣(ひとえ)」を着分けるだけでなく、夏には「絽(ろ)」や「紗(しゃ)」といった透け感のある生地を用いるなど、気候に合わせた着こなしも、昔の人の豊かな知恵と言えます。
専門家の視点
昔の着物は、まさに「循環型の衣服」でした。布を無駄にせず、形を変えて世代を超えて受け継いでいく。現代のSDGsの考え方を、昔の日本人はごく自然に実践していたのですね。この精神性こそ、着物文化の最も美しい部分かもしれません。
昔と今の違いを比較してみよう
昔の着物と現代の着物は、基本的な形こそ同じですが、その背景にある考え方や具体的な仕様には様々な違いがあります。ここでは、その違いをいくつかの重要なポイントで比較してみましょう。これを理解することで、アンティーク着物と現代の着物の両方の魅力がより深くわかります。
| 項目 | 昔の着物(主に江戸時代) | 現代の着物 |
|---|---|---|
| 着用シーン | 仕事、家事、お出かけなど、日々の暮らし全般(日常着) | 冠婚葬祭、式典、お茶会、趣味などの特別な日(ハレ着) |
| 素材 | 絹、麻、木綿などの天然繊維が中心。手織りの布も多い。 | 絹のほか、手入れのしやすいポリエステルなどの化学繊維も多い。 |
| サイズ | 個人の体型に合わせて一枚ずつ仕立てるのが基本(誂え) | プレタポルテ(既製品)が多く、S・M・Lなどのサイズ展開がある。 |
| 着付け | 補正をあまりせず、体の線に自然に沿わせる。比較的ゆったり。 | タオルやパッドで補正し、直線的な寸胴体型を作って着崩れを防ぐ。 |
| 帯の長さ・幅 | 比較的短く、幅も狭め。結び方もシンプルで実用的なものが多かった。 | 長く、幅も広い。帯締め・帯揚げを使い、多様で華やかな結び方ができる。 |
| 価格・入手 | 高価なものは家の財産。庶民は自作したり、古着を再利用した。 | 高級品から手頃な価格帯まで幅広い。レンタルサービスも普及している。 |
特に大きな違いは、やはり「日常着」であったか「ハレ着」であるかという点です。日常着だった昔は、動きやすさや手入れのしやすさ、着心地の良さが何よりも重視されました。一方で現代は、特別な日に着るものとして、見た目の美しさや写真映え、そして定められたTPOを守るための「格」の高さがより重要視される傾向にあります。そのため、着付けの方法も、昔の自然な着こなしから、現代の補正をしっかりして長時間着崩れを防ぐスタイルへと大きく変化していきました。和装の市場規模も、経済産業省の報告書によると、ライフスタイルの変化と共に大きく変わってきたことが示されています。
時代で変わる色や柄のトレンド
着物の色や柄は、その時代の社会情勢や人々の美意識、流行を映し出す鏡のような存在です。各時代のトレンドを知ることで、お手持ちの古い着物がいつ頃のものか推測する手がかりにもなり、その魅力がより深く理解できます。
江戸時代:「粋」と「わびさび」の美学
江戸時代のトレンドカラーは、「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」に代表される、微妙な色合いの茶色や鼠色でした。これは、幕府の奢侈禁止令により派手な色が制限されたため、庶民がその制約の中で洗練された色の違いを楽しんだ結果です。柄は、遠目には無地に見えるほど細かい江戸小紋や、シンプルな縞(しま)模様、格子(こうし)模様が「粋」であるとされました。また、麻の葉や青海波、亀甲といった、長寿や繁栄を願う吉祥文様(きっしょうもんよう)も広く愛されました。
明治時代:文明開化の鮮やかな色彩
西洋文化の影響を受け、ドイツから安価な化学染料(アニリン染料)が輸入されるようになると、これまでにはなかった紫、赤、ビビッドな緑などの鮮やかな色が爆発的に流行します。柄も、バラや蝶、唐草模様といった西洋風のデザインや、新聞や機関車など文明開化を象徴するモチーフが取り入れられました。日本の伝統柄と西洋のデザインが融合した、ダイナミックで斬新な模様がこの時代の大きな特徴です。
大正時代:「大正ロマン」の華やかなデザイン

「大正ロマン」と呼ばれるこの時代は、個人の自由や表現が尊重され、ロマンチックで個性的なファッションが花開きました。竹久夢二に代表されるような抒情的な美人画の影響も大きく、アール・ヌーヴォーやアール・デコといった西洋の芸術様式を取り入れた、流れるような曲線的で大胆な柄が人気を集めます。菊や牡丹、椿などの花を大きく描き、明るいパステルカラーや、紫、ワインレッドといった深みのある色で彩るなど、華やかで叙情的なデザインが若い女性を中心に絶大な支持を得ました。
昭和時代:レトロポップな魅力
戦前のモダンな流れを引き継ぎつつ、戦後は大量生産技術の発展と共に、より大衆的でポップなデザインが登場します。映画や雑誌の普及も相まって、抽象的な幾何学模様や、サイケデリックな色使い、デフォルメされた大きな花柄など、どこか懐かしさを感じさせる「昭和レトロ」と呼ばれるスタイルが確立されました。特に銘仙(めいせん)などの手頃な絹織物に多く見られ、現代でもアンティーク着物として根強い人気があります。
身分で異なった素材と仕立て
厳格な封建社会であった江戸時代、着物は単なる衣服ではなく、その人の身分や社会的地位を示す重要な役割を持っていました。そのため、身分によって着用できる素材や色、柄には厳しいルールが存在し、一目でその人の立場がわかるようになっていました。
武士の着物
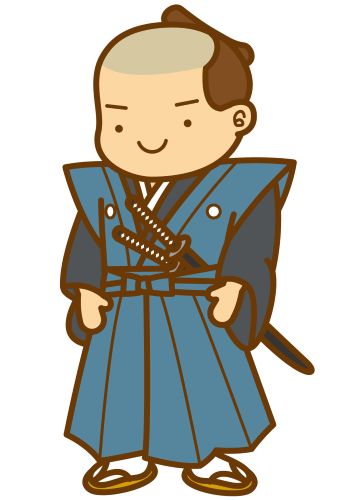
武士の正装は、「裃(かみしも)」でした。これは肩が張った独特の形の上着(肩衣)と袴を組み合わせたもので、素材は主に格式を示す麻が用いられました。公式な場では、家格を示す家紋を染め抜いた紋付を着用しました。紋の数(五つ紋、三つ紋、一つ紋)で格が異なり、五つ紋が最も格式高いものとされました。普段着は木綿や絹の着物を着用していましたが、色は黒や紺、茶色などの質実剛健なものが基本で、華美な装いは避けられました。
町人の着物
経済力を持ち、文化の担い手でもあった町人たちは、法律で許される範囲で最大限のおしゃれを楽しみました。前述の通り、江戸小紋のように一見地味でも実は非常に精緻で手が込んでいる、という「粋」な着こなしを好みました。裕福な商人は、表地は木綿でも、人目につかない裏地に豪華な絹を使ったり、見えない羽裏(はうら)に有名な絵師に絵を描かせたりする「裏勝り(うらまさり)」という、究極の「隠れたおしゃれ」を競い合いました。
農民の着物

日本の人口の大半を占めていた農民の衣服は、何よりも機能性と耐久性が重視されました。素材は、自ら栽培することもあった麻や木綿が中心です。色は、汚れが目立ちにくく、染めが容易で安価な藍色がほとんどでした。これらは「野良着(のらぎ)」と呼ばれ、作業のしやすいように丈を短くしたり、擦り切れたら何度も繕ったり、布を継ぎ足したりしながら、一枚の着物を大切に着続けていたのです。布を補強し、保温性を高めるために施された「刺し子」も、厳しい生活から生まれた用の美と言えるでしょう。
例えば、庶民が武士の特権であった紫や、非常に高価で手間のかかる総絞りの着物を着ることは、原則として許されていませんでした。歌舞伎役者が派手な衣装で人気を博すと、それが風紀を乱すとして禁止されることもありました。このように、着物は単なるファッションではなく、社会秩序を維持するための重要なツールでもあったのです。
昔の着物での暮らし:日常の着こなし術
着物が日常着だった時代、人々はどのように着物と付き合っていたのでしょうか。現代の私たちの生活からは想像もつかないような、下着や寝間着、そして驚きのお手入れの方法など。現代とは大きく異なる日常の着こなし術から、昔の人のリアルな暮らしぶりが見えてきます。
- なぜパンツを履かないのが普通だった?
- 寝巻きとしての着物の役割
- 昔の着物の洗濯と手入れ方法
- 妊娠中の着物の着こなし
なぜパンツを履かないのが普通だった?
「昔の人はパンツを履かなかった」という話は有名ですが、これは決して下着を着けずに無防備だったという意味ではありません。現代の私たちが考える「下着を着けない」という感覚とは異なり、その背景には着物という衣服の構造と、当時の文化が深く関わっています。結論から言うと、現代のようなズロース型やパンティ型の「パンツ」というものが、そもそも日本に存在しなかったため、履くことができなかったのです。
では、下半身は何も身に着けていなかったのかというと、そうではありません。女性は「湯文字(ゆもじ)」や「腰巻(こしまき)」と呼ばれる、巻きスカートのような一枚の布を身に着けていました。これは下着としての役割だけでなく、着物の裾さばきを良くしたり、裾がはだけた時に直接肌が見えるのを防いだり、保温したりと、多くの目的がありました。素材は肌に優しく吸湿性の良い木綿や麻が一般的でした。
男性の下着は、ご存知の通り「裃(ふんどし)」が主流でした。こちらも、現在のパンツとは形状が大きく異なり、一枚の長い布を体に巻き付けて使用するものです。
つまり、「パンツを履かない」のは、そうした形のものが文化としてなかったからであり、下着の概念自体がなかったわけではないのです。着物という重ね着を基本とする服装の中で、理にかなった下着の形が湯文字や褌だったと言えます。
昭和7年に起きた白木屋百貨店の火事で、多くの女性が亡くなった逸話は有名です。その原因の一つとして、「着物の裾が乱れて下半身が見えるのを恥じらい、救助の縄梯子を使うのをためらったため」と言われています。この悲劇的な事件をきっかけに、日本女性の間に活動しやすい洋式のパンツが急速に普及した、という説があります。
寝巻きとしての着物の役割
現代では肌触りの良いパジャマやルームウェアが寝巻きの主流ですが、昔は昼間に着ていた着物をそのまま寝巻きにすることも珍しくありませんでした。特に庶民の間では、仕事着を脱いだ後、少し着崩してリラックスした状態で就寝することもあったようです。しかし、上流階級や裕福な家庭、また一般家庭でも、就寝時専用の衣服がきちんと存在していました。
その代表格が「寝巻き(ねまき)」や「浴衣(ゆかた)」です。浴衣は元々、蒸し風呂に入る際に着た「湯帷子(ゆかたびら)」が起源で、それが風呂上がりに着る室内着(湯上がり着)となり、やがてその着心地の良さから寝巻きとしても広く使われるようになりました。素材は汗をよく吸い、肌触りの良い木綿が一般的で、仕立ても昼間の着物より簡素なものが多かったのです。
帯も、昼間のような硬く幅の広いものではなく、兵児帯(へこおび)や細い紐状のものを、体を締め付けないように軽く結ぶ程度でした。これは、質の良い睡眠を妨げないための、理にかなった工夫でした。
また、着物の下に着る「長襦袢(ながじゅばん)」が古くなったものを、寝巻き代わりにすることも一般的でした。特に肌触りの良い正絹の襦袢は、快適な寝巻きとして重宝されました。冬場には、綿入りの「掻巻(かいまき)」という、着物の形をした掛け布団のようなものを使い、厳しい寒さをしのいでいました。
昔の着物の洗濯と手入れ方法

合成洗剤も全自動洗濯機もなかった時代、着物の手入れは家族総出で行う大変な重労働であり、専門的な技術が必要な作業でした。特に高価な絹の着物は、その素材の特性上、家庭で安易に丸洗いすることはできません。では、一体どのように洗濯していたのでしょうか。
その答えが「洗い張り(あらいはり)」という、驚くべき洗濯方法です。これは、着物を一度すべて解いてパーツごとの布の状態に戻し、一枚一枚を洗い、板や竹の伸子(しんし)という道具を使って生地に張りを持たせながら乾かす方法です。洗い終わったら、布の風合いを保つために布海苔(ふのり)などで糊付けをして乾かし、再び手縫いで着物に仕立て直します。この一連の作業によって、生地の縮みや型崩れを防ぎながら、染めの風合いを損なわずに汚れをきれいに落とすことができました。
木綿や麻の普段着は比較的丈夫なため、家庭で洗うこともありましたが、それでもタライでの手洗いが基本で、大変な手間と時間がかかりました。
このように、昔の人々は着物を「洗う」のではなく、「解いて、洗い、張り、また縫う」という非常に手間のかかる工程を経て手入れをしていました。これは、一枚の着物をいかに大切に、そして長く着続けようとしていたかの証左です。
洗い張りは専門的な知識と技術を要するため、現代では「悉皆屋(しっかいや)」と呼ばれる着物の手入れを専門とする職人に依頼するのが一般的です。貴重な古い着物を自分で洗濯しようとすると、生地を irreparably 傷めたり、色落ちさせたりする可能性があるため、まずは専門家に相談することが不可欠です。
妊娠中の着物の着こなし
現代のように機能的で多様なマタニティウェアがなかった時代、妊婦さんは大きくなるお腹とどう付き合い、どのように着物を着ていたのでしょうか。実は、着物はその構造自体が、妊娠中の女性の体型変化にも驚くほど柔軟に対応できる、非常に優れた衣服でした。
その秘密は、着付けの基本である「おはしょり」と、仕立ての工夫である「身幅(みはば)」にあります。着物は、実際の身丈よりも長く作り、着る際に腰のあたりで布を折り上げて着る「おはしょり」で丈を調整します。お腹が大きくなってくると、このおはしょりの折り上げ分が自然と少なくなることで、前身頃の丈が長くなり、大きなお腹をすっぽりと優しく包むことができたのです。
また、身幅が足りなくなってきた場合でも、前述の通り着物は直線裁ちで縫い代(ぬいしろ)が内側にたっぷりととってあります。そのため、脇の縫い目を一度解き、縫い代を出して縫い直す(これを「脇を出す」と言います)ことで、簡単に身幅を広くすることが可能でした。
帯も、お腹を圧迫しないように、通常より高い位置である胸の下で結んだり、腹部を支えるように柔らかい布(腹帯)を巻いた上から軽く結んだりするなどの工夫がされていました。日本では、安産を願って妊娠5ヶ月目の「戌(いぬ)の日」に腹帯を巻く「帯祝い」という風習が今も残っています。このように、昔の女性は特別なマタニティ着物をあつらえることなく、手持ちの着物と先人の知恵で快適に過ごしていたのです。これは、着物の構造そのものが持つ「許容範囲の広さ」と「順応性」の証明と言えるでしょう。
昔の着物の文化を今に活かす
この記事では、昔の着物に関する壮大な歴史や、時代ごとの文化、そして現代とは大きく異なる人々のリアルな暮らしについて詳しく解説しました。着物は単なる衣服ではなく、日本の精神文化そのものを映し出す鏡のような存在です。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。
- 着物の原型は平安時代の「直線裁ち」に確立された
- 直線裁ちは体型を選ばず再利用も容易なサステナブルな技法だった
- 江戸時代に庶民文化が花開き「粋」という独特の美意識が生まれた
- 明治以降は西洋文化の影響で色や柄が多様化し華やかになった
- 昔の着物は日常着であり現代の着物はハレ着が中心という大きな違いがある
- 素材は絹・麻・木綿といった天然繊維が主で仕立て直しが前提だった
- 昔の着付けは補正をあまりせず体の線に沿わせる自然な着姿だった
- 色や柄には各時代の社会情勢や流行が色濃く反映されている
- 江戸時代は身分によって着物の素材や仕立てに厳格な決まりがあった
- 昔の女性はパンツではなく湯文字や腰巻という下着を着用した
- 寝巻きには着心地の良い浴衣や古くなった長襦袢が使われた
- 洗濯は一度解いてから洗い再び縫い直す「洗い張り」が基本だった
- 着物はその構造上、妊娠中の体型変化にも柔軟に対応できた
- 昔の着物文化には現代のSDGsに通じるモノを大切にする知恵が詰まっている
- 昔の文化や背景を知ることで着物をより深く多角的に楽しむことができる






